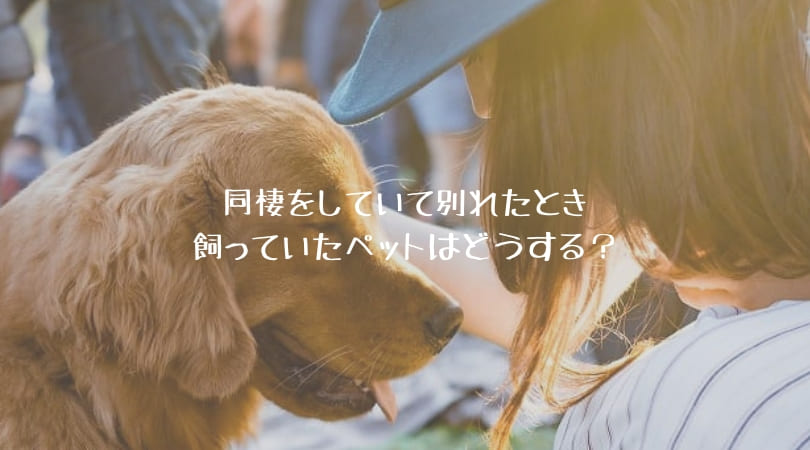最近ではペット可の物件が増えてきたのもあり、同棲中に2人で犬や猫などのペットを飼っているケースも多くなっています。
2人が仲良く同棲生活がうまくいっている間は、ペットがどちらが飼っているかは問題となりません。
同棲生活が破たんして2人が別れを選んだ場合にペットの引き取り手が問題となります。

同棲生活を解消することになったけど、どうしてもペットを引き取りたい!

同棲生活を解消するにあたって、どちらもペットを引き取れずに困った!
など、ペットをどちらが引き取るかで困っている人もいます。今回は、
- どちらかがペットを引き取るケース
- どちらもペットを引き取りたいケース
- どちらもペットを引き取れないケース
にわけて、同棲を解消するときにペットをどうするかのお悩みについて、解決方法を提案していきますので、参考にしてください。
同棲して別れるときに、どちらかがペットを引き取る場合

まず、一番問題なくすむのが、どちらかがペットを引き取ると決まっている場合です。
同棲の前からペットがいた場合にその元の飼い主である人が引き取るなどのケースです。
同棲中に飼いはじめたペットであっても、よりペットをしっかりと面倒を見れるほうが引き取るのであれば問題ありません。
もし、ペットを引き取りたいと思っている人が感情的に主張しているだけで、しっかりと面倒を見ることができないような状態であると感じられる場合。
こういう場合はペットの幸せのためにしっかりと話し合うようにしましょう。
同棲を解消して別れた後、お互いに連絡をとらないほうが良いケースも多いのですが、ペットがいた場合には、友達としてお互いに連絡をとりあってペットについて報告するのもよいのではないでしょうか。
ペットを相手に渡したくない!どちらも引き取りたいケース

同棲していて、ペットが可愛くなってしまいどちらも引き取りたいということで、トラブルになるケースもあります。
どちらが引き取ってもペットの面倒をしっかりと見れるのであれば、話し合いでペットをどちらが引き取るのかをまずは決めましょう。
引き取らないことになった人は同棲を解消すると決めた結果であるので、あきらめるしかありません。
しかし、相手にペットを引き渡すのは不安があって、どうしてもペットを引き取りたい!という人もいます。
ペットを引き取りたいというトラブルになった場合、どのように解決するのがよいのかをみていきましょう。
ペットは法律上は「物」!?所有者が誰かが問題となる
ペットは大切な家族ですが、法律上は残念ながら「物」と扱われます。
「物」の所有権、つまり持ち主は誰になるのかを考えると、ペットショップなどで購入した場合には、お金を出した人と判断される可能性が高いのです。
動物愛護団体や愛護センターなどから引き取ったペットについては、ペットの譲渡契約書を交わすことが多いです
この場合には譲渡契約書に譲受人として署名した人が所有者として判断される可能性が高くなります。
迷い猫をそのまま飼っている場合など所有者が分からない場合には、世話をしていた人が所有者と判断される可能性が高くなります。
どちらもお金を負担している、どちらも世話をしていた場合には、そのペットは2人の「共有」になります。
「共有」の場合は、どちらにも所有する権利があるので、ペットの場合は2人で話しあって解決するしかありません。
どうしても話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所の調停や裁判で決めることになります。
同棲を解消して別れるリスクを考えてペットを飼おう!
同棲中にペットを飼う場合、ペットの幸せを考えて、同棲を解消して2人が別れたときに備えましょう。
同棲中に絶対に一生仲良くしていこうと思っていても、大切なペットのためにいざというときの備えをすることも大切です。
ペットのお金をどちらか一方が出す場合でも、ペットの世話を積極的にしたいと思っている人の名義で、購入、市役所の登録、保険の登録をしておくとよいでしょう。
もしも同棲解消でトラブルになったときに、これらの名義の人が調停や裁判で所有者と認められやすくなります。
すでに飼いはじめていて、どうしても引き取りたい場合は?
所有権はともかく、相手にペットを引き渡すのが不安な場合、なんとしてでも引き取りたい場合にはどうしたらよいのでしょうか。
まずは2人で話し合う
同棲期間中に一緒にペットを飼ってきたのであれば、ペットを介して2人で仲良く楽しい時間をすごしたこともあると思います。
ペットの幸せのためにどちらが引き取るのが良いのかを、まずは2人でしっかりと話し合ってみましょう。
家族や友人に説得してもらう
同棲して別れるときには感情的になり、ペットの面倒を見られないと思っていても意地になってペットを引き取ると主張している場合もあります。
その場合には、家族や友人など相手が信頼していて意見を聞いてくれそうな人に相談し、相手を説得してもらうように頼むとよいでしょう。
動物愛護団体に相談する
相手にペットを引き渡すと面倒を見てくれなかったり虐待の危険がある場合には、動物愛護団体に相談してみるのも1つの方法です。
動物愛護団体の方は、ペットに関する法律や条例に詳しく、親身になって相談してくれるでしょう。
ただし、動物愛護団体はボランティア団体で、その団体によって得意分野も違います。
また、多くのトラブルと関わっているため忙しいので、なるべく要点をまとめて相談をするとよいと思います。
弁護士に相談する
ペットも大切な家族の一員です。
お金はかかってしまいますが、ペットを守るために弁護士に相談するのも1つの方法です。
法律的な観点からのアドバイスをもらえますし、調停や裁判の手続きもしてくれます。
裁判になる覚悟でペットを引き取りたいことを主張することで、ペットを真剣に面倒を見る気がない人であれば、あきらめてペットを引き渡してくれるケースも多いですよ!
とはいえ、弁護といってもカテゴリの幅が広いので自分で探すのは骨がおれます。
ペット相談など、法律の専門家を探すなら相談サポートを利用すると便利です。
同棲して別れるときに、どちらもペットを引き取ることができない事情がある場合

同棲して別れるときに、
「新しい彼と同棲生活をスタートすることになったけど、新しい彼が猫アレルギーで、猫を引き取れない…」
「同棲生活を解消して2人とも引っ越すことにしたが、2人とも新しく住むところがペット禁止のマンションで、ペットをどちらも引き取れない…」
などと、どうしてもペットを引き取れない場合もあります。
ペットを飼うことができない事情があったとしても、ペットを捨てたり殺処分するために動物愛護センターに持ち込むのは、絶対にしないでくださいね。
同棲生活を解消するからといってペットを捨てたり殺処分したりしたら、あとから心残りとなって新しい生活をスタートできません。
ペットのためだけでなく自分のためにも、責任をもってペットに新しい家族を見つけてあげましょう。
ここでは、新しい飼い主を探すための方法をご紹介しますが、ペットも信頼している家族から引き離されることで、とても悲しい思いをしてしまいます。
まずはもう一度、本当にペットを2人とも飼うことができないのかどうか、考え直してみてください。
家族や友人にペットを飼えないか相談する
ペット好きな人の家族や友人には、ペット好きな人も多いものです。
どうしても飼うことができない事情を話し、信頼できる家族や友人に引き取ってもらうという方法だと、後からペットの様子をみることもできて安心です。
殺処分ゼロの動物愛護センターに相談する
最近では、行政でもペットの殺処分ゼロを目指して動物の引き取り手を探しています。
殺処分ゼロの実績が続く動物愛護センターであれば、殺処分される心配も少ないので、事情を話して引き取ってもらうことができるでしょう。
ただし、ペットを引き取るほどの事情ではないと判断されれば、引き取ってもらえない可能性もあります。
動物愛護団体に相談する
動物愛護団体では、特に犬や猫であれば動物の引き取り手を常時探しています。
動物愛護団体に相談して、ペットの里親を探してもらうようにお願いするという方法があります。
動物愛護団体はボランティア団体なので、引き取り手のないたくさんの犬や猫の里親探しに忙しいことが多いので、いくつかのボランティア団体にあたってみることが必要かもしれません。
同棲後に別れたときに飼っていたペットの対応:まとめ
同棲生活を解消して2人が別れるときには、自分たちの感情で手いっぱいかもしれませんが、ペットも大切な家族の一員です。
自分たちは別れたいと思っていても、ペットは家族と別れたくないと思っています。
そのことを踏まえて、責任をもってペットを飼うことができる人が引き取ることができるように話し合いを進めましょう。
どちらも引き取るという主張をしている場合には、法律的な所有権が問題となるので、ペットを飼うときに、ペットの世話をしたいと思っている人の名義で購入や登録しておくことをおすすめします。
どうしてもどちらも引き取ることができない場合には、責任をもってペットに新しい家族を見つけてあげてください。
また、自分たちで解決できないときはまずは無料で相談できる相談サポートなどを利用して、きちんと対応していきましょうね。